【とこぽへんしゅう部がおとどけする「とこポスト」 キッズばん】この人、知ってる?実はスゴイ!クイズでわかる「とちぎ偉人伝(いじんでん)」

みんなが住んでいる、とちぎ。
実は、とちぎにゆかりのある人たちには、とってもスゴイ人たちがたくさんいるんだよ。
この記事では、とちぎにゆかりのある人たちを題ざいとしたクイズを4問出題するよ。
キミは答えられるかな?では、スタート!
第1問!

豊秋「那須与一図」(渡辺美術館所蔵)
さいしょにしょうかいするのは、「那須与一(なすのよいち)」。
国語でも習う『平家物語』に登場する、平安時代のぶしょうだよ。『平家物語』はぶしである「源氏(げんじ)」と「平氏(へいし)」のたたかいをえがいたお話。
那須与一は、とちぎの那須(なす)のあたりで力を持っていた「那須氏(なすし)」のひとり。『平家物語』の「屋島(やしま)のたたかい」の場面で、源氏の代表として、海にうかんではげしくゆれる船の上にかかげられた、おうぎを矢でいぬいたことで有名な、弓矢の名人なんだ。
さて、この那須与一だけど、「与一(よいち)」という名前には、どんな由来があるでしょう?
(A)「すぐれた一つの才のうを与(あた)えられた人」という意味
(B)生まれたじゅん番にちなんで
(C)「よい地」に字を当てた
(D)父親の名前を一字もらった
答えは…
「(B)生まれたじゅん番にちなんで」です!
「与一(よいち)」は「余一(よいち)」と書くこともあり、「十あまり一」という意味だよ。つまり、与一は「十一男」、11番目に生まれた男の子だったんだね。きょうだいがいっぱいだね!
☆もっとくわしく知りたくなったら

●行ってみよう!
那須与一伝承館(なすのよいちでんしょうかん)
大田原市南金丸1584-6
那須与一の活やくを、からくり人形風ロボットとスクリーンのえいぞうでさいげんしたげき場があったり、かん係するしりょうもてんじされているよ。
第2問!

つぎにしょうかいするのは、「蒲生君平(がもうくんぺい)」。
蒲生君平は、江戸(えど)時代の学者だよ。今の宇都宮市で生まれ、こどものころから学問がすきで、いっぱい勉強したんだって。
大人になってからは、天のうのおはかとされる、日本中の古墳(こふん)を調べて、本にまとめたよ。
古墳って知ってるかな?むかしむかしの古墳時代につくられた、とっても大きなおはかで、小学校でも社会の時間に習うよ。古墳の中でも、とくに有名な形といえば、丸と四角を組み合わせたような形の「前方後円墳(ぜんぽうこうえんふん)」。日本のあちこちにたくさんのこっていて、まるで山みたいにきょ大なものもあるよ。
実は、この「前方後円墳」という名前をつけたのが、蒲生君平なんだ。この名づけは、蒲生君平が「前方後円墳」は、あるものをかたどった形だと考えたからなんだよ。さて、その「あるもの」とは何でしょう?
(A)家
(B)人
(C)車
(D)かぎあな
答えは…
「(C)車」です!
蒲生君平は、「前方後円墳」を、牛などが引く昔の車をかたどったものだと考えたんだって。そこで、四角い部分は車を引く取っ手の部分、丸い部分は死んだ人が乗る車本体の部分と考え、「四角い部分(方)」が前、「丸い部分(円)」が後ろ、として名前をつけたんだね。
でも、今でも蒲生君平の考えが正しかったのかどうかはわかっていません。本当に、車の形なのか、四角が前で丸が後ろなのかはナゾのまま。キミはどう思う?ぜひ考えをめぐらせてみてね。いつかわかる日が来るのかな?楽しみだね!
☆もっとくわしく知りたくなったら

●行ってみよう!
蒲生君平勅旌碑(がもうくんぺいちょくせいひ)
宇都宮市花房3丁目
https://utsunomiya-8story.jp/search_post/蒲生君平勅旌碑
蒲生君平の行いや本などをたたえるため、明治(めいじ)時代になってから、明治天のうが宇都宮藩知事(うつのみやはんちじ)にたてさせた、きねんひだよ。
第3問!

3番目にしょうかいするのは、「二宮尊徳(にのみやそんとく)」。
二宮尊徳は、江戸(えど)時代に、あれてしまった農村をもう一度立て直すことに、リーダーとして力を注いだ人だよ。「二宮金次郎(にのみやきんじろう)」ともよばれ、昭和のころに、日本中の学校の校庭に、二宮金次郎のぞうがたくさんたてられたことでも有名だね。
二宮尊徳は、今の真岡市二宮町(もおかしにのみやまち)のあたりにあった「桜町(さくらまち)」の立て直しもまかされ、みごとに成功させたんだ。
さて、立て直しのために二宮尊徳が行ったことのひとつに、「村人を表しょうするせい度をつくった」があるんだけど、この表しょうされる人を、二宮尊徳はどうやってえらんだでしょう?
(A)村人どうしの投ひょうでえらんだ
(B)家がらでえらんだ
(C)おさめた年ぐの多さでえらんだ
(D)年れいでえらんだ
答えは…
「(A)村人どうしの投ひょうでえらんだ」です!
二宮尊徳は、村を何回も見回り、村人のようすをよく理かいしました。そして、農業への意よくを高めるため、すぐれた作物を生さんした人を表しょうするせい度を取り入れました。二宮尊徳が大切にしたのは、表しょうされる人は、村人どうしの投ひょうでえらぶこと。
表しょうされた人は、ごほうびとして、クワやカマなどの農具やお金がもらえたんだって。それなら、きっとやる気も出てくるね!
☆もっとくわしく知りたくなったら
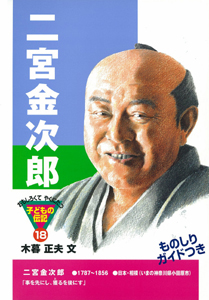
●読んでみよう!
二宮金次郎
ポプラ社
子どものころからよくはたらき、勉強ねっ心だった金次郎。そのちえとけいけんを生かして農みんを指どうし、たくさんのまずしい農村をすくいます。
第4問!
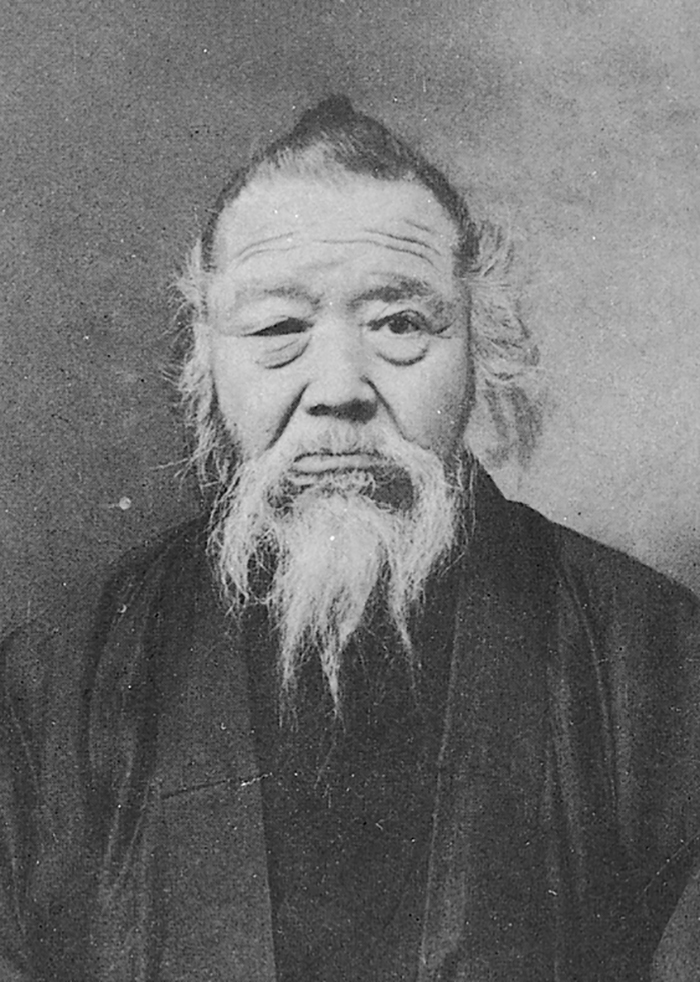
出典:国立国会図書館「近代日本人の肖像」(https://www.ndl.go.jp/portrait/)
さいごにしょうかいするのは、「田中正造(たなかしょうぞう)」。
田中正造は、江戸(えど)時代に今の佐野市(さのし)に生まれたよ。そして、明治(めいじ)時代に、第1回しゅうぎ院ぎ員に当せん!
そのころ、とちぎの渡良瀬川(わたらせがわ)の下流では、問題が起こっていたんだ。もともと米のよくとれる、ゆたかな土地だったけど、足尾銅山(あしおどうざん)の工場から流れ出る水が原いんで、作物がかれて育たなくなったり、井戸水を飲んだ人が「げり」をする、小さなこどもが死ぼうするなど、人々のけんこうにもおそろしいえいきょうが出ていたんだよ。しかも、明治23年に、大こう水が起こったことで、あたり一面に足尾銅山の鉱毒(こうどく)が流れこみ、大きなひがいが広がったんだ。
この「足尾銅山鉱毒事件(あしおどうざんこうどくじけん)」は、日本ではじめて問題になった公がい問題で、田中正造は、そのかい決のために一生をささげた人だよ。
さて、田中正造が「足尾銅山鉱毒事件」をかい決するために、【やっていない】ことは、どれでしょう?
(A)国会でえんぜつする
(B)せん門家に原いんを調さしてもらう
(C)天のうに直せつうったえる
(D)遊水地をつくってこう水をふせぐ
答えは…
「(D)遊水地をつくってこう水をふせぐ」です!
しゅうぎ院ぎ員だった田中正造は、国会で「せいふはすぐに銅(どう)の生さんをやめさせてほしい」とえんぜつしたり、今の東京大学の先生にたのんで、ひがいの原いんをつきとめたりしたけど、一向に問題はかい決しなかったんだ。
そこで、田中正造は、命がけのかくごを決め、明治天のうの乗る馬車に直せつ問題をうったえたんだけど、すぐにけいさつにつかまってしまった。でも、このことがきっかけとなって、問題が世の中に広く知られ、とうとう問題はかい決に向けて動き出すことになった。
政府は、渡良瀬川(わたらせがわ)などの川が集まる場所にあった谷中村(やなかむら)をつぶして、そこに遊水地をつくってこう水をふせぐ計画を立てたんだけど、それでは本当のかい決にはならないと、田中正造は反対したんだ。それでもけっきょく、遊水地はつくられた。それが、今の渡良瀬遊水地(わたらせゆうすいち)だよ。
☆もっとくわしく知りたくなったら
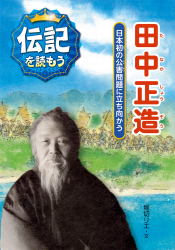
●読んでみよう!
田中正造 日本初の公害問題に立ち向かう
絵/石井勉
あかね書房
人々の命を守るため、大きなけん力に真正面からぶつかって、自分の意しをつらぬいた正造。何度もろう屋に入れられたりしながら、決してあきらめず、地いも名もすてて、力のかぎりたたかいぬいた人生とは。
このクイズを、とちぎにゆかりのある人について知るきっかけに
どうだった?クイズにはいくつ正解できたかな?
み力てきな人たちがいっぱい登場したね!ひょっとしたら、キミのそんけいする人や、目ひょうとする人も見つかったかも?
気になったら、ぜひこのクイズをきっかけに、とちぎにゆかりのある人をもっとくわしく調べてみよう!
※この記事は、「とちぎふるさと学習」(栃木県教育委員会)の「とちぎのひと」の2024年8月10日掲載のページを参考に作成しています。