【とこぽへんしゅう部がおとどけする「とこポスト」 キッズばん】とちぎにもおにがいた!? せつ分にちなむ「とちぎようかいでんせつ」
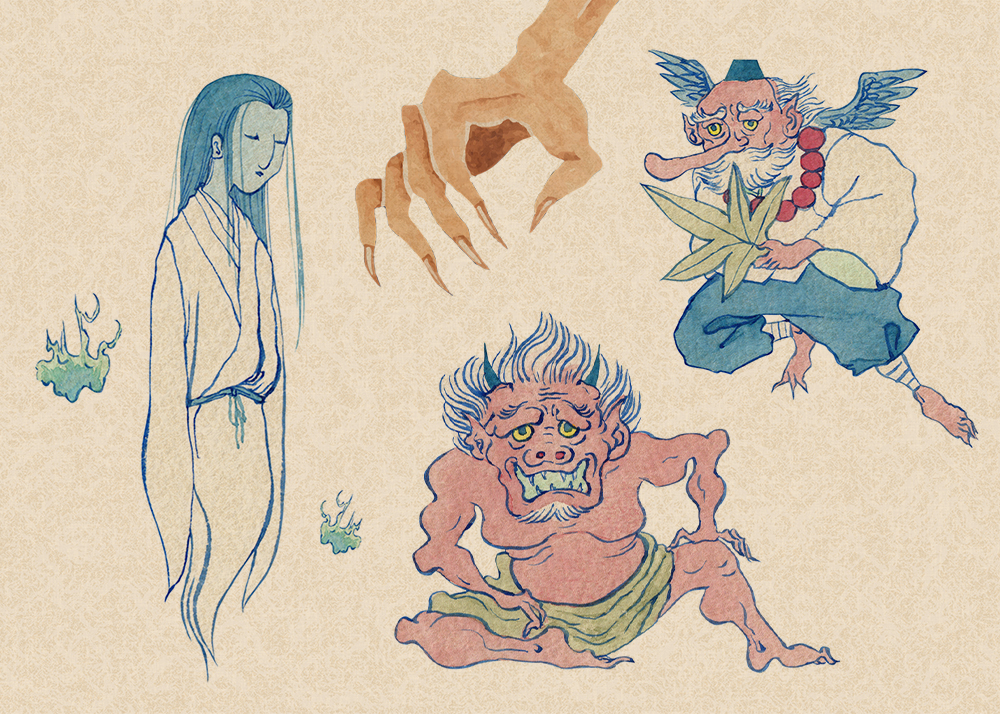
2月2日は、せつ分。せつ分といえば、「おには外!」のかけごえでおなじみだね。
さて、とちぎにも「おにがいた」というでんせつがあるって知ってるかな?
おにのほかにも、とちぎには、さまざまなようかいのお話がのこっているよ。
さあ、どんなようかいだろう?ドキドキしながら読んでみて!
身長3メートル!きょ大なおに「百目鬼(どうめき)」
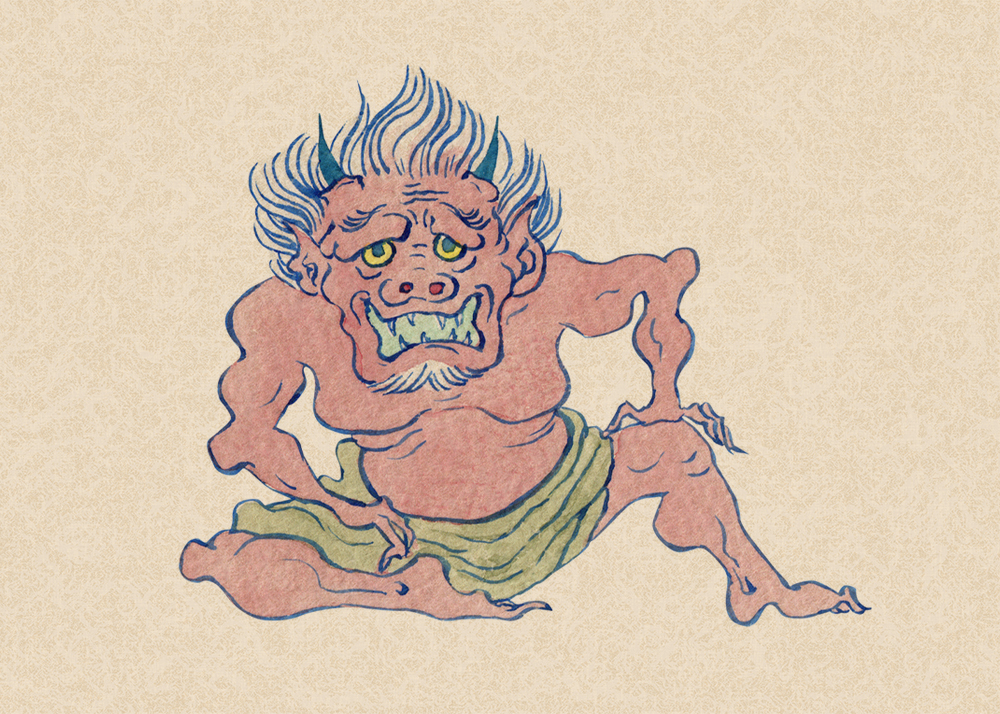
むかしむかしの平安時代、今の宇都宮市(うつのみやし)のお話だよ。
田原藤太(たわらのとうた)というぶしが歩いていると、知らないおじいさんに出会ったんだ。そのおじいさんは、「大曽(おおぞ)の里の北西にある兎田(うさぎだ)に行け」と言った。その兎田というのはね、死んだ馬をすてる「馬すて場」といわれる、気味の悪いところだったんだって。
田原藤太がおじいさんに言われた通り、兎田に行き、しばらく待っていると……
身長が3メートルもある、でっかいおにがとつぜんあらわれて、いきなり死んだ馬に食いついた!
こわいよね、ビックリするよね!でもね、田原藤太はそこで「ギャー!」とさけんだり、にげ出したりはしなかった。
落ち着いて、弓を引きしぼり、一本の矢を放った!その矢はおにのむねにみごと命中!おにはにげ出したものの、ばったりと倒れたんだ。
おにがいなくなった後、兎田は「塙田(はなわだ)」と名前もかわり、人が住むようになったんだって。
このおにだけど、「百目鬼(どうめき)」とよばれているんだ。百目鬼は、漢字で「百の目のおに」と書いて、「どうめき」と読むんだけど、これは、百目鬼がその名の通り「100この目を持っていたから」とも、「100ぴきのおにの頭目(とうもく、カシラのこと)だったから」とも言われているよ。
ちなみに、「塙田(はなわだ)」は今でも宇都宮市の地名にあって、栃木県庁(とちぎけんちょう)があるところも「塙田」だよ。そして、栃木県庁の近くには「百目鬼通り(どうめきどおり)」という通りがあって、おにのでんせつを今につたえているよ。
よくばりのおばあさんを地ごくにつれていく「おにのつめ」

むかしむかし、金かしと米屋をしている、よくばりのおばあさんがいたんだ。
このおばあさんの家には、大きな「買いマス」と小さな「売りマス」があった。
村人が米を売りに来たときは、おばあさんは大きな「買いマス」ではかって買うんだ。そうすると、同じお金でたくさんのお米を買うことができるね。
でも、村人がお米を買いに来たときには、おばあさんは小さな「売りマス」ではかって売る。つまり、同じお金でも少しのお米しかわたさない、ということ。……とんでもない、インチキだね!
そんなよくばりだから、村人からはきらわれていたおばあさんだけど、じゅ命でとうとう死んでしまった。
その夜、おばあさんのおそう式をたん当することになった、お寺のおぼうさんの前にあらわれたのは、なんと地ごくから来たおに!おには、自分は地ごくのえんま大王の使いだと名乗った。
「このおばあさんは地ごく行きが決まっている。だから、おそう式に出るひつようはない」
そう言われても、「はい、そうですか」とは引き下がれないおぼうさんは、おにを追い返したんだ。
いよいよ次の日のおそう式当日、ひつぎを運ぶ行列がおはかに向かっていると、急にビューッと強い風がふき、大雨がザーザーふってきた。さらに、黒い雲からあらわれたのは、長いつめのついたきょ大な手!きょ大な手は、おばあさんの入ったひつぎをグイッとつかんで、空中に持ち上げた。
みんなおどろいてこしをぬかしてしまったけど、おぼうさんだけはゆう気を出して「ほっす(お坊さんが使う、ふさふさした毛のついた法具)」で、「手」をさっとはらったんだ。
すると、おそろしい悲鳴が聞こえて、ひつぎは地面に落ち、あたりはパッと明るくなった。ひつぎの近くには、お坊さんに払い落とされたおにのつめが落ちていたんだって。
同じお話は、真岡市(もおかし)や益子町(ましこまち)などにつたわっているよ。
ふぶきといっしょにやってくる「雪女」
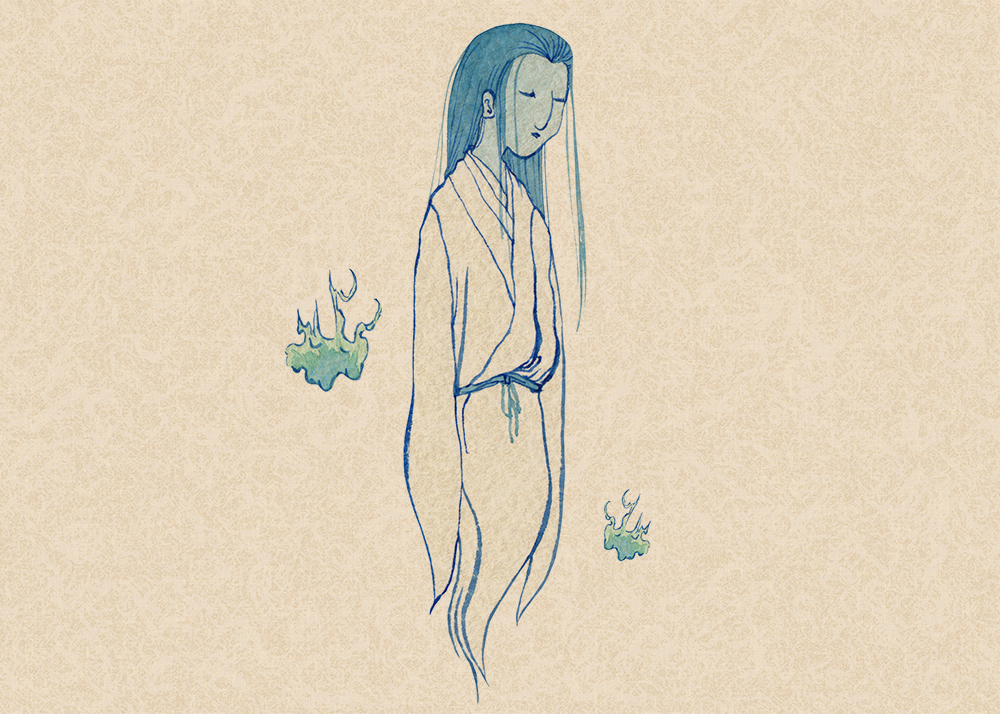
むかしむかし、今の那須郡那須町(なすぐんなすまち)の湯本温せんのお話だよ。
温泉では、村人が交代で小屋に寝泊まりして、温せんの番をしていたんだって。
あるとき、政右衛門(まさえもん)という人が当番になったんだけど、すごいふぶきの夜にひとりでいると、戸をどんどんとたたく音がするんだよ。
「何だろう?」と戸を開けると、きれいな女の人が立っていて、「一ばんとめてください」とたのむんだ。政右衛門は、「こんな大雪の中、ひとりでやってくるなんてあやしいな、キツネかタヌキが化けているのかも?」と思ったけど、「どうしてもとめてほしい」とたのまれて、とめることにした。
次の朝、女の人は「ありがとうございました」と言い、とめてくれたお礼に、自分のかみの毛にさしていた、くしとかんざしを政右衛門に手わたすと、またふぶきの中に消えていったんだって。
「ああよかった」と政右衛門がくしとかんざしを持って、小屋に外に出ると、おどろいたことに雪なんてふってなくて、外はいいお天気!しかも、もらったくしとかんざしは、日光に当てるとみるみるうちにとけてなくなってしまった。
後で、政右衛門から話を聞いた村人たちは、「きっとその女の人は、雪女だったんだよ」と言い合ったんだって。
どこへだってひとっとび!「てんぐ」になったわかもの

むかしむかし、今の鹿沼市(かぬまし)のお話だよ。
酒野谷(さけのや)というところに、次郎作(じろさく)というわかものがいたんだけど、この人は山や川に遊びにいっては、何カ月も帰ってこなかったり、ふしぎな行動をしていたんだって。
ある日の朝早く、次郎作は、お母さんに「今日は加波山(かばさん、茨城県にある筑波連山の山)の神社のお祭りだから、行ってくる。お赤はんをたいておいてくれ」と言いのこして出かけていった。
言われたとおり、お母さんがお赤はんをたいていると、「ああつかれた」と次郎作が帰ってきた。お母さんは、びっくりぎょうてん。だって、酒野谷から加波山までは、50kmもあるんだよ。ふつうの人が歩く速さ、時速4kmで歩いていくと、かた道だけでも12時間はかかってしまう計算なんだ。昔のことだから、自動車や電車なんてないし、自転車だってまだない。どんなにがんばって歩いたって、こんなに早く帰ってこられるわけがないんだよ。
でも、次郎作は「本当に行ってきたぞ、ほら」と新しいおふだも出して見せて、「つかれたから、ちょっとねる。でも、ねているところをけっして見るなよ」と言って、となりの部屋でねてしまった。
「いくら何でもおかしいな」と思ったお母さんは、ふすまをそっと開けてのぞいて見た。
すると……部屋の中では、鼻の長いてんぐのすがたになった次郎作が、部屋いっぱいに羽根を広げてぐーぐーねていたんだって。次郎作は、神社までてんぐの羽根でとんでいって、帰ってきていたんだね。
はっと目をさました次郎作は、「見られてしまっては、もうここにはいられない」と、どこかへとんでいってしまったんだって。
[参考文献]
日向野徳久『栃木の民話第一集』[新版]日本の民話32,未來社,2016
日向野徳久『栃木の民話第二集』[新版]日本の民話39,未來社,2016
下野民俗研究会『読みがたり 栃木のむかし話』,日本標準,2004
栃木の民話語り かまどの会『親と子で語る うつのみやの民話』,随想舎,2011
小杉義雄『鹿沼のむかし話』,栃の葉書房,1987
栃木県教育委員会「とちぎふるさと学習」とちぎの民話
宇都宮市歴史文化資源活用 推進協議会「宇都宮の歴史と文化財」宇都宮にまつわる民話